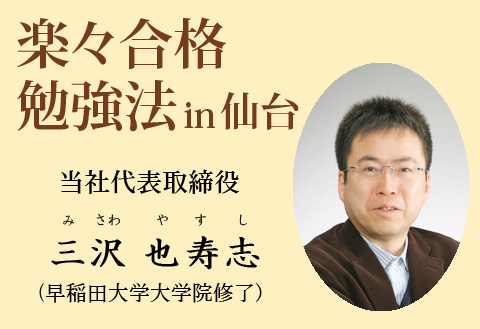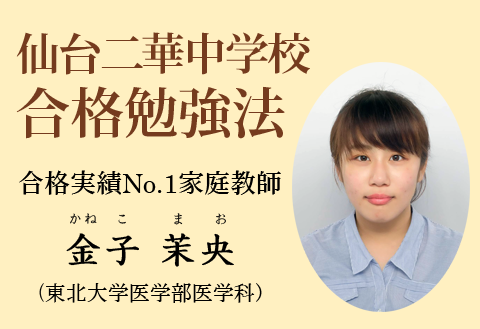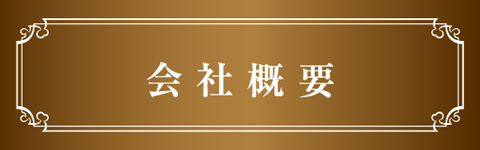楽で成績が上がる「英語」勉強法:教科書丸暗記
皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

今日は、誰でも楽に出来てすごく成績が上がる「英語」勉強法をお教えします。 中高生の皆さんは、ぜひ最後までご覧下さい。 必ず役に立ちます。
1. 教科書を丸暗記する
その英語勉強法とは、事前に本文中の分からない単語を辞書で調べたら、その後は教科書を何度も繰り返して音読して丸暗記する、ただそれだけです。 英語の教科書全てを丸暗記するので時間は掛かりますが、なすべきことは繰り返し音読することだけなので、難しいことは少しもありません。
言うまでもなく、同じ読むにしても、黙読よりもより多くの感覚器官を使う音読の方がよく頭に入りますので、自宅などそれが可能な場所では必ず音読して下さい。
英語の教科書の例
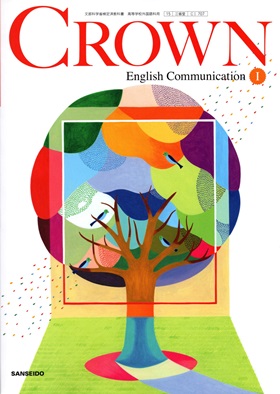
英作文などの力もUP!
これだけで英語の成績が上がるのか疑問に思われる方も多いでしょうが、実際その効果は抜群です。 僕もこの「教科書丸暗記法」で英語を勉強し続けて、TOEFLの要求水準が高いSydney大学大学院に留学することが出来ました。 また、英文をすべて暗記するので、当然のことながら、英作文や穴埋め問題の成績も大幅に向上します。
後付けで文法も分かる
加えて、具体的な英文を先に覚えるので、後付けで「それは文法で言うとこういうことなんだな。」とすんなり分かるようになるので、文法の力も大きく向上します。 これに対して、抽象的な英文法だけを先に覚えようとすると、人間の頭にはものすごく大変な作業となります。
2. 絶対に単語帳を作るな!
それから、単語帳を作るなどして、単語だけを抜き出して覚えようとしては絶対にいけません。 単語も、丸暗記の際に文章中で覚えるようにして下さい。 単語だけを覚えようとしてもすごく覚えづらいですし、その意味だけを覚えても実際に使えるようにはなかなかなりません。
覚えるチャンクが大きい方が
暗記に際しては、覚えるチャンク(塊り)がある程度大きい方が、後で記憶を引き出しやすいものです。 それに加えて、文章中で単語を覚えると、単語使時用のTPOも一緒に覚えられます。 ですから、英単語を覚えるのにも、文章を丸ごと覚える「教科書丸暗記法」が一番優れています。
そして、付け加えれば、単語だけ暗記しようとした場合と違って、うんうん唸って頭が痛くなったりしなくて済むというメリットもあります。
3. すぐにやってみて下さい
この教科書丸暗記法は、上述のように教科書を何度も音読して丸暗記するだけで英語の成績が大きく向上するし、かつ誰でも簡単に出来ることなので、中高生の皆さんは今すぐにこの勉強法を始めて下さい。 今まで英語が苦手だった生徒さんほど、この勉強法の簡単さと効果の大きさに驚くことと思います。
共通テスト【数学Ⅰ・A】解法 & 勉強方法
受験生の皆さん、こんにちは! 仙台市の『名門進学会』家庭教師で東北大学医学部医学科3年の金子 茉央(かねこ まお)です

今日は、大学入試共通テスト【数学I・A】の、高得点を取れる「解法」&「勉強法」をお話し致します。 数学に関しては、難易度や問題構成は以前のセンター試験とあまり変わりませんが、少し雰囲気が変わり、考えさせられる問題になっています。
1. 出題形式
大問5題構成。
第1問、第2問は必答。第3~5問はいずれか2問を選択して解答する。
時間70分、満点100点。
2. 試験の解き進め方
全ての試験について言えることですが、テスト中に一番守らなくてはならないもの、それは「時間」です。 大問5題なので、私は各大問につき最大15分ずつ割り振っていました。 第1問と第2問は比較的典型問題なのでなるべく早く解くようにし、たまに捻った問題の出る第3〜5問に時間を割くようにしていました。
必ず見直しの時間を取る
そして忘れてはならないのは、見直しの時間です! 共通テストの何より恐ろしいところは、ミスをしてしまうとその問題を解ける人が一定数いるために差をつけられてしまうところです。 特に、本番の極限に緊張した環境では何が起こるか分かりません。 必ず見直しの時間は取って下さい。
ミスをしにくい問題を選択する
皆さんは、選択問題何を選んでいますか? 選び方の基準は、問題の好み、得意なもの、ぱっと見の解きやすさなど色々あると思いますが、私は基本的に整数の性質と図形の性質を選んでいました。 なぜならば、答えを出したときにミスをしていない確信が持ちやすいからです。
もちろん、問題の種類によっては確率を選ぶこともありましたが、ミスを減らすべく選択問題を選ぶようになってからは、大分数学の正答率が上がっていきました。 ここら辺の判断基準については、また後ほど書きます。
3. 各大問の対策と試験勉強
私は、センター試験・共通テストの数学は、公式の典型的な使い方を如何に正しく理解しているかが鍵だと思っています。 点数が取れないとき、やるべきことは過去問や予想問題の解説を読み、問題と対応させることです。
どういう条件が出ているときにどういう公式を使っていくのかがおおよその流れがあって、問題の中できちんと誘導されていることに気付くはずです。 以下では各大問についてお伝えしていきます。
A. 大問1(数と式、二次関数、図形と計量)
二次方程式のポイント
まず、二次方程式についてです。 二次方程式を解くコツは、余計な係数を省いてグラフをシンプルに見てグラフの形をイメージすることです。「Y=Ax2+Bx+C」*の形になっているはずです。 2021年の問題では2×2+(4c-3)x+2c2―c―11=0という問題が出ましたが、この場合もA=2、B=4c-3、C=2c2―c―11と見なすことができます。
以下のルールを覚えて下さい
今回の問題でもありましたが、cにある値を代入することは、*のグラフの係数を変化させていることに過ぎません。 係数が変わることは、グラフが平行移動していることに過ぎません。 これを理解するには、以下のルールをぜひ覚えて下さい。
● A>0なら下に凸(逆は逆)。 Aはグラフの形を決める。
● B/A>0ならグラフの軸は負の領域(逆は逆)。 Bが変化するとグラフはx軸方向に平行移動する。
● C>0ならy切片は正(逆は逆)。 Cが変化するとグラフはy軸方向に平行移動する。
これらのルールは、恐らく二次方程式を習ったころに言われたことだと思います。 当たり前のことだと思われるかも知れませんが、この情報さえあればy―xグラフのおおよその位置や動きが把握できます。 そして、求めた答えが大体あっているか視覚的に確認出来ることにより、ミスを減らし自信を持って次の問題に進むことが出来ます。
図形問題のポイント
次に、図形の問題です。 2021年の問題は正方形や三角形の面積をcosθやsinθの公式に絡めて解くという面白い問題でした。 図形の問題は、まずわかる限りの情報(角度や辺の長さ)を図の中に書き込んでください。 その上で、初めて問題を解き始めます。
(3)の問題を例に取ると
2021年(3)の問題を例に取ってみると、△AIDの面積=1/2ac・sin(180-B)=1/2ac・sinB=△ABCの面積となります。 同様に他の三角形も求めていくと、結局△ABCの面積に行き着くという問題でしたが、きちんと情報を書き込んでいくことで三角形の面積を迷わずに導き出すことが出来ます。
(2)・(4)の問題は
また、(2)・(4)の問題は、三角関数の公式に注目します。(2)の問題では、cos A=(b^2+c^2ーa^2)/2bcの余弦定理に注目すると、Aが鋭角か否かによって面積の大小関係が定まることが分かりますし、(4)では外接円の半径が2r=a/sinAで求められることに気づけば苦労せずに問題を解くことが出来ます。
思考力問題に対応するために
共通テストは、思考力が問われるテストと言われています。 通り一遍等の解き方で問題に取り組んでいても解けない問題が、これから先出てくるかもしれません。
色々な解き方を知っておく
私は、学校の授業の一環で、典型問題と言われる易しい問題をなるべく多くの別解を用いて解くということをしていました。 一つの問題を解く際に別解を知っていると言うことは、その問題を色々な視点から見ることが出来ると言うことです。 すこぶる煩雑で時間を浪費してしまう解き方もあれば、魔法のように一瞬で答えが導き出せる解き方もあります。
最良のアプローチをする
受験は、時間との勝負です。 毎回煩雑な解き方をしていれば解き終わらないし、一方で魔法の解き方は使える場合が限られていることが多いです。 そこで、どちらも知っていることが求められます。 自分の知っているアプローチの中からもっとも賢い解き方を選択し、煮詰まった時に最終手段として煩雑な解き方を持っていることが理想です。
もちろん言うは易しなので、そう簡単に問題を達観することはできませんが、余裕がある時に別解を知っておこうとする努力は大切です。 私は、模試の問題で解けた問題であっても一応解説に一通り目を通すようにしていました。
B. 大問2(二次関数、データの分析)
新規単位は定義を確認
2021年度の問題では、タイム・ピッチ・ストライドと言う見慣れない単位が出てきました。 しかし、見慣れない言葉に出会っても焦らず落ち着いて考えることが大事です。 私は、新しく単位を認識する時、必ずその単位を定義する式を確認します。
今回であれば、ストライド(m/歩):一歩で何m進めるのか、ピッチ(歩/秒):1秒で何歩歩けるのか、です。 こうやって単位について自分の頭を整理しておくと、その後に考えさせられる平均速度:1秒に何m進めるのかについても、自然とストライドとピッチを掛け算すれば良いと考えられます。
データ分析は慣れ
まずは、最低限の知識を入れることです。 過去問をいくつか見てみると、自ずと知っておくべきデータの値が分かってくると思います。 私は、この範囲に苦手意識を持っていて模試を解くたびに何かしらの間違いをしていましたが、繰り返し問題に触れるうちに、丁寧に数えてグラフを対応させていけば必ず解けること、そしてパターン問題が多いことに気づきました。
丁寧に解けば解けると言いましたが、これは時間制限のある共通テストですので、いかにこの範囲に時間を割けるかも課題です。
C. 大問3(場合の数と確率)
誘導に乗ること
2021年は、条件付き確率の問題でした。 問題自体は典型問題で、難易度は高くないですが、ポイントは問題の誘導に如何にきちんと乗ることが出来るかです。 会話文の中で作問者が解答者に考えさせたいことを理解して、丁寧に解いていきましょう。 そして、これはチャンスでもあります。
誘導があるということは、普段の考え方とは別の解き方をさせたいと言うことです。 それは、普段の解き方でも解けばもれなく確かめ算をすることになり、答えが一致したら安心して次の問題に進むことが出来ます。
全体の事象の意識
私は、確率や場合の数は、全体の事象を意識して解くようにしていました。 具体的に言うと、確率であれば各事象を足したら1になることであり、場合の数であれば全ての事象を書き出すと言うことです。 もちろん時間のかかる方法ですので最初は普通に解きますが、残りの事象を把握しておくと答えへの自信に繋がります。
D. 大問4(整数の性質)
選択問題としておすすめ
基本的に典型問題が多く、問題文では様々なゲームが提示されつつも、一次不定方程式の整数解を導く問題となることが多いです。 不定方程式を満たす数字を調べること、xとyの一般式を出すこと、xとyの解の範囲に注意することが出来れば、大体の問題は誘導に乗って解いていけるはずです。 大きい値になった時には、計算ミスには注意して下さい。
比較的解きやすくミスも生じにくい上、方程式に当てはめて計算すれば確かめ算も出来るので、私はこの大問を選ぶことが多かったです。
E. 大問5(図形の性質)
完答が難しい
図形は、得意不得意分かれるところだと思います。 個人的な感想としては、テスト中の緊張感の中では気付くべきことに気付けず完答が難しかったので、選択することは少なかったです。
図は正確に
図形問題対策としては2つあります。1つ目は図を正確に書くことです。 長さの大小のみならず角度も鋭角、鈍角、直角いずれなのか正確に書きます。 特に、有名な直角三角形は必ず覚えて下さい。 直角であることに気づけるか否かは、正答率を大きく左右します。
公式は頭に叩き込む
問われ方に対する公式の用い方をきっちり把握しておくことは、とても大事なことです。 例えば、4つの点が円上にあることを示すには?と聞かれたら、方べきの定理の逆か円周角の定理の逆を使えばいいのだなというようにです。 図形上に情報は無限にありますが、使うべき公式は限られています。
公式のアテを初めにつけることが出来れば、図形問題は大分解きやすくなります。
4. 最後に
長くなってしまいましたが、いかがだったでしょうか? 受験生の皆さんの数学試験対策の手助けに少しでもなれば、私としてもとても幸いです。 皆さんは、カリキュラムの変わり目に当たってしまってとても大変な思いをしているとは思いますが、ぜひ頑張って下さい。
成績向上「ポモドーロ勉強法」短時間集中!
児童・生徒の皆さん、その親御さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

今日は、目一杯集中して勉強できるテクニックを皆さんにお教えしますので、最後まで読んで実践して下さい。 その成績アップへの効果は、抜群です。
1. ポモドーロ・テクニック
それは、「ポモドーロ・テクニック」と呼ばれている有名なものです。 その内容は、まず学年によってタイマーを10~25分にセットします(学年によってタイマーをセットする時間は、下記3. 4. 5.に書いています)。 そして、セットしたタイマーが鳴るまでの時間は一心不乱に集中して勉強するのです。
この時間は、スマホやマンガなどに気を取られてはいけません。 10~25分と短い時間ですので、この間はひたすら集中して勉強して下さい。
ひたすら集中して勉強を
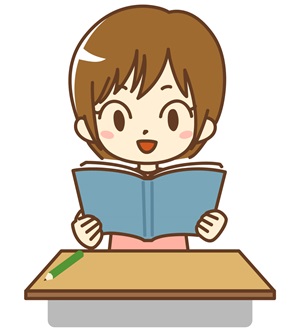
漫然と長時間勉強するよりも
集中力に自信がない生徒さんでも、10~25分限定ならば勉強に集中できるはずです。 そして、間に適当な休憩とご褒美をはさんで、この10~25分の間集中して勉強することを何セットか繰り返します。 重要なことなので後でも述べますが、そうすれば、漫然と長い時間勉強するよりも遥かに学力がUPします。
ポモドーロとはタイマーの名前
ところで、皆さんが何だろうと思っている「ポモドーロ」とは、この方法を考え出した人物のキッチンタイマーの名前で、イタリア語でトマトという意味です(ご存じの方も多いかも知れませんが、ポモドーロというパスタ料理もあります)。
2. 「ポモドーロ勉強法」の準備
適切なタイマーを事前に準備すること以外には、自分の周りから「スマホやパソコン・ゲーム機・マンガ」といった気を引き勉強の邪魔になるものを遠ざけておきましょう。 そうすれば、集中力を乱される可能性がより一層低くなります。
タイマーの例

3. 小学生の「ポモドーロ勉強法」
小学生の場合長い時間集中することが困難なので、低学年ではタイマーを10分くらい、高学年では15分くらいにセットして勉強しましょう。 難関中学を受験をするのでない限り、高学年でも合計90分くらいの勉強で十分です。 そのくらいの時間でも集中できれば、それだけでも小学生の成績は十分に向上します。
4. 中学生の「ポモドーロ勉強法」
中学生の場合は、タイマーを20分くらいにセットして、集中した勉強を可能な限り繰り返します。 とは言え、難関校を受験するのでない限り、3年生になるまではそこまでシャカリキになる必要はありません。 3年生になったら「志望校の難易度と自分の学力のギャップ」に合わせて、このポモドーロ勉強法を何セットも行って下さい。
5. 高校生の「ポモドーロ勉強法」
高校生の場合は、タイマーを集中力が続く最大限の25分にセットして、この25分の集中した勉強を可能な限りのセット数繰り返して下さい。 この方法は、もちろん、友人と一緒に勉強する場合にも使えます。 やってみれば、この方法を知った友人にも感謝されることは間違いありません。
6. やってみれば効果に驚くはず
最後に、前にも書きましたが、漫然と勉強を長時間行うよりも、集中したポモドーロ勉強法を何セットか行う方が、学力は遥かに向上します。 簡単に出来ることなので、皆さんもこのポモドーロ勉強法をやってみて下さい。 きっとその効果に驚くはずです。
ハーバード大学推奨:スモールウイン勉強法
児童・生徒の皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

1. 勉強に自信が持てない生徒さんのために
今日は、勉強に自信が持てずやる気がわかないという生徒さんのために、スモールウイン勉強法をお教えします。 スモールウインとは、文字通りの小さな勝利という意味です。 このブログでは、勉強における「小さな勝利」を積み重ねて自信とやる気を取り戻す方法を書いていますが、Harvard Business Reviewでもビジネスにおいてこの方法を推奨しています。
Harvard Business Reviewの1冊

2. 現状より少し勉強時間を増やす
やる気がわかない生徒さんが、いきなり勉強時間を大幅に増やそうとするのは現実的ではありません。 そこで、まずは、今よりも1/4時間(15分)だけ増やすことを目標として下さい。 これくらいであれば、達成することそれほどは難しくはないと思います。
達成すれば自信が湧いてくる
このような小さなことでも、達成(スモールウイン)すれば、誰しも自信が湧いてくるものです。 一般に自信とやる気は連動するので、そうすれば、さらに多くの時間勉強しようという意欲も湧いてきます。 これが、「スモールウイン勉強法」の第一ステップです。
少しでも余計に勉強を

3. 薄い参考書を覚えこむ
次に、具体的な「スモールウイン勉強法」として、薄い参考書を1冊覚えこみましょう。 厚くてたくさんの事柄が書いてある参考書は、読むだけでも大変で、内容を覚えこむことは更に大変です。 そこで、まずは、基礎的な事柄が書いてある薄い参考書を読み込んで、その内容を覚えましょう。
覚えれば自信になる
薄いとはいえ参考書の内容を覚えこめば自信にもなり、それ以降のテストでもある程度の成績が取れるようになります。 そうすれば、より網羅的な参考書を読み込もうという気持ちにもなります。 これが、「スモールウイン勉強法」の第二ステップです。
3. 現状より少し上の成績を目指す
さて、いきなり現状より大幅な成績向上を目指しても、目標の高さに頭がくらくらするだけで、やる気が湧いてくることはまずありません。 そこで、学校のテストなどで現状の点数プラス10点とか、現状より席次10番アップとか、今までよもり少し余計に頑張れば出来そうな目標を立てます。 そうすればやる気も湧いてきて、目標の成績も達成出来ることが多くなります。
ここまでくればしめたもの!
そして、目標の成績を達成すれば、それがまた自分の中での自信となり、更なるやる気が湧いてきます。 これが、「スモールウイン勉強法」の第三ステップです。 自信の無かった生徒さんがここまで来れば、しめたものです。 こうなったら、ためらわずに更に上を目指しましょう!
やる気を引き出す「勉強のゲーム化」
皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

1. 勉強にゲームの要素を取り入れる
今日は、「お子様がスマホばかり見てて(あるいは、ゲームばかりやっていて)勉強してくれない。」などと悩む親御さんのために、勉強にゲームの要素を取り入れてお子様により長時間勉強させる方策を書きました。 これらは、当社のお客様に実際にやって頂いてとても効果があったものですので、皆様もぜひ最後までご覧下さい。
2. ポイントカードシステム
1つ目のゲーム化は、「ポイントカードシステム」です。 ゲームでも、多くのポイントを獲得してステージをクリアするために夢中で頑張ってしまうことが良くありますが、それを勉強に応用するのです。
ポイントカード

A. まずは努力を引き出す
ここでは、まず結果よりも努力を引き出すために、「勉強時間をポイント化」します。 1時間勉強したら1ポイントとして、3ポイント貯まるごとに1時間スマホを見てよい、あるいはゲームをやってよい、などとするのです。 そして、100ポイント毎にお子様が欲しがっているちょっとした物を買ってあげる、などとします。
B. カードは簡単なものでOK!
ポイントカードは、コピー用紙などにワープロで作成しても良いし、もちろん定規などを使って手書きしてもよいです。 簡単に作れるもので構いません。 そして、それに(それのマス目に)親御さんが赤のボールペンなどで印(ポイント)を記入していけばOK!です。
こんな簡単なことで、お子様の勉強意欲は飛躍的にUPして、だらだらとスマホを見続けることもなくなります。 騙されたと思って、まずはここからやってみて下さい。
3. テストの成績によるボーナス
次は、成果を引き出すためのゲーム化です。 ゲームでも成果を出せばボーナスを得られるので、ボーナス欲しさに延々とゲームをやってしまうことがよくあります。 例えば、僕も、トップを取るまで麻雀ゲームを延々とやってしまうことが今でもあります(これを書くのは恥ずかしかったのですが)。
A. ボーナスの条件を決めておいて
この、ゲームにおけるモチベーションの獲得し方を、勉強に応用します。 事前にボーナスをプレゼントするテストの成績(点数でも席次でも偏差値でもOK!)と与えるボーナスの内容ををお子様と話し合って決めておいて、テストの結果がその成績をクリアしたら約束したボーナスを与えます。
ボーナスの例

B. 達成意欲を高める
ボーナスの内容は、お子様の学年にもよりますが、「条件をクリアしたら、ファミレスで好きなものを食べさせてあげる。」くらいで構いません。 沢山のお金をかける必要は全くありませんので、これもぜひやってみて下さい。 この方策は、特に、達成意欲がそれほど高くないお子様の達成意欲を高めるのに役立ちます。
4. 姑息でも合格に役立つ
僕が書いた上記2つの方策を読んで、姑息だなあと思われた親御さんもいらっしゃるかと思います。 でも、こういった方策が、お子様がスマホやゲームに誘惑される時間を減らして、その分勉強時間を確実に増やします。 そして、そのことが、最終的に志望校合格に役立ちますので、ぜひ上記2つともやってみて下さい。 受験は、精神論より志望校に合格することが第一です。
東大などの【数学】考え方&解法
受験生の皆さん、こんにちは! 仙台市の『名門進学会』家庭教師で東北大学医学部医学科2年の金子 茉央(かねこ まお)です

1. お疲れ様でした!
皆さんは、怒涛の日々が過ぎ去り、ようやく一息つけた頃でしょうか? 中には、気持ちを切り替えて、後期試験に向けて勉強に取り組んでいる方もいらっしゃるのでしょうか? 何はともあれ、本当にお疲れ様でした。
サクラ咲ケの赤べこ

2. 難問に挑戦した過去
皆さんは、東大の問題を解いたことありますか? 一度触れたことがある人ならお分かりだと思いますが、東大の問題は期待を裏切らずものすごく難しいです。 私の志望校は高3の春に決まりましたが、難問を解く力を身につけるべく東大・京大・東工大といった難問を出すことで有名な大学の問題も積極的に解いていました。
受験目前には東大の問題でも
中には何度問題文を読んでも手も足も出ない問題すらあって、始めの頃は気が遠くなるような思いをしたことをよく覚えています。 でも、私は受験を目前に控えた頃には、東大の問題に対して以前のような忌避感は覚えなくなっていました。
東大などの赤本
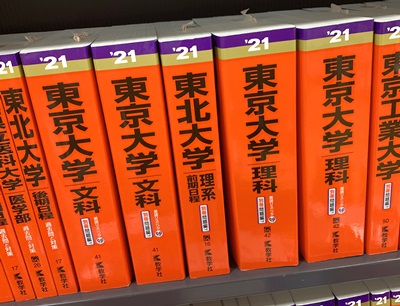
3. 難問を解くときの考え方・解法
どうしてなのか? そこで、今回は、「数学」や「理科」の難しい問題を解く時の考え方や解法についてお話ししていきます。
A.「難問」へのアプローチ
「難問」と言われる問題は、何がその問題を難問たらしめているのでしょうか? いかに大学の教授が作った難しい問題といえども、高校生の知っている知識や公式で解けなくてはなりません。 高校生の知っている知識や公式を用いて解くことの出来る数学の典型は、すなわちチャートの例題です。
青チャートの例
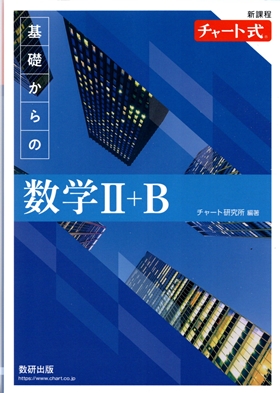
使ったことのある人ならお分かりだと思いますが、チャート(私は青チャートを用いていました)は、公式ごとに定型の問題文に対して、最も効率の良い解き方が示されています。 そして私は、ほとんどの難問は何らかの閃きや解釈によって、これらのパターン問題に「落とし込む」ことが出来ると思っています。
B. 自分の知っている問題に「落とし込む」
手も足も出ないのは、自分が見たことがない問題だからです。 ならば、自分の知っている「チャートのパターン問題に落とし込める」ように頑張れば良いのです。 そう考え始めてからは、見たことのない問題であっても「解ける訳がない!」という忌避感を感じなくなりました。
いわゆる難関校の問題は
とは言っても、青チャートの例題はしっかりやり込めば偏差値60くらいになるので、パターン問題と言っても皆が解けるわけではありません。 そこを当たり前に解けるものとして提示してくるのが、いわゆる難関校の問題であるように感じます。
C. 自分にあったレベルから着実に
今、難関校の問題が全く解けないと感じる人は、是非とも「自分がどの段階でつまずいているのか」解答を読んで確かめて下さい。 難問を自分の知っているパターン問題に落とし込む所で手こずっているのか、それとも次の段階のパターン問題をきちんと身につけていないのか。
よく使っていた問題集
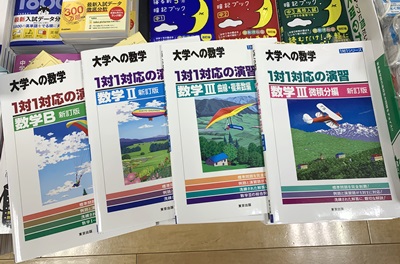
もう一度解き直して
後者である場合は、チャートレベルの問題集を今一度解き直して下さい。 数学の問題集は、無闇に難易度の高いものに手をつけてはいけません。 難しい問題集は、その1ランク下の問題集が解けることを前提として構成されていますから、それがきちんと解けるようになってから次に進むべきです。
忌避感を和らげられたら
難問への取り組み方について自分なりの考え方をお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか? もちろんこれは1個人の意見なので、皆さんも自分なりの考え方で難問にアプローチして頂ければと思います。 私の勉強法で、皆さんの忌避感を少しでも和らげられたら幸いです。 最後まで読んで頂きまして、有難うございました。
宮城県高校入試「過去問演習」を徹底的に!
皆さん、こんにちは。 仙台市で家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

1. 最も効率の良い勉強方法を
高校入試まで残りの日数も段々少なくなってきて、多少焦っている受験生やその親御さんもいらっしゃるのではないかと思います。 今日は、そうした方々に向けて、受験に向けてこれからでも出来る最も効率の良い勉強方法をお教えします。 知れば合格可能性が大きく上がりますので、最後までご覧下さい。
2. 本試験と一番傾向が似ているのは「過去問」
間違いなく言えることは、筆記試験ならどんなものでも、その年度の本試験と一番傾向が似ているのが、その試験で今までに出題されてきた問題、いわゆる過去問です。 決して、本試験出題者とは別の組織が作成した「模試の問題」や「対策問題」ではありません。
出題する組織が同じなのだから
ですから、宮城県の高校入試の場合でも、来春の本試験と一番傾向が似ているのは、今までにこの試験で出題されてきた問題である「過去問」です。 出題する組織が(そして、多くの場合出題する人物も)同じなのだから、これは当然のことです。
仙台市の受験生の皆さんも、このように志望校合格にとても役立つ「過去問」を購入して、何度も解いてみて下さい。 このブログの最後「4.」で、最も効果的な過去問演習の方法をお教えしますので、ぜひその通りに実行して下さい。
3. 書店で「過去問集」を購入する
宮城県内の高校入試問題過去問集(大体過去5年分)は、県立高校も私立高校も今年の分が既に出版されていて、Amazonや仙台市内の書店で普通に購入出来ます。
当社にある「宮城県立高校入試過去問集」
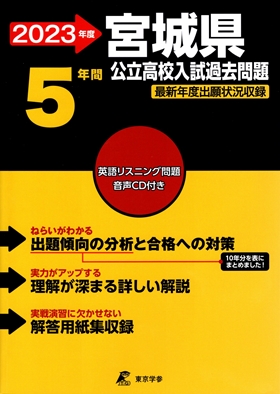
税込み1,650円
受験生は必ず購入して下さい
例えば、宮城県立高校の過去問集は上記写真のもので、値段も税込み1,400円と安いです。 ですから、県立高校を受験される方は必ず購入しましょう。
また、宮城県内私立高校の過去問集は、1校当たりでは県立高校過去問集より売れる冊数がずっと少なくなるので、その分値段が2千円台後半になります。 県立高校のものよりも大分値段は高くなりますが、宮城県内の私立高校を受験する方は、自分が受験する高校の分は惜しまずに購入して下さい。
当社にある私立高校入試過去問集の例
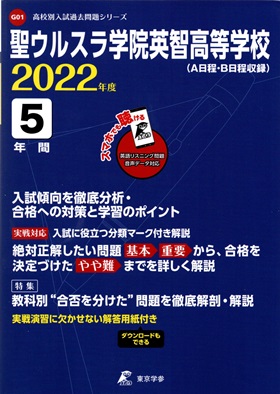
4.「過去問」演習の方法
最後に、これまでずっと高い合格実績を上げ続けている当「名門進学会」代表の三沢が、このブログ「2.」でお約束したように、宮城県内の高校受験生の皆さんに、これからの時期の「最も効果的な過去問演習の方法」をお教えします。
まず、過去問集を購入したら、すぐに2年前の過去問を解いて下さい。 解いてみて、あまり出来なくとも構いません。 それでも、1回でも過去問を解いてみれば、今までの入試でどのような問題が出題されていたか分かるはずです。
入試問題に合わせた勉強を
そして、入試でどのような問題が出題されていたか分かれば、今後は、それに合わせて焦点を絞った効率的な勉強が出来ます。 今の時期に過去問を解いておく最大の目的は、このこと、つまり、今後的を絞った効率的な勉強をするためです。
出題に合わせて効率的な勉強を
次いで、全ての過去問を精読します。 それから、年末までは過去問の出題内容に合わせた勉強(時々過去問を眺めながら)を続けて下さい。 勉強が進んだ年末に、残りの過去問を全部解いて下さい。 そして、その後は、過去問を解いて出来なかった問題を解けるように勉強を進めて下さい。
入試1ヶ月前は「全ての過去問×5回」解く!
そのようにして勉強を進めて、入試1ヶ月前になったら、過去問集に載っている「全5年分の問題を5回ずつ」解いて下さい。 解いてみて、その時にまだ出来なかった問題は、必ず入試までに解けるようにしておいて下さい。
高い確率で合格出来る
上記の方法でしっかりと勉強出来れば、現時点で合格可能性が五分五分の受験生でも、高い確率で志望校に合格出来ます。 当「名門進学会」は、この勉強方法を取ってもらうことによって、必ずしも成績が良い訳ではなかった受験生を数多く志望校に合格させてきました。
このブログをご覧の受験生の親御さんも、志望校の過去問集をすぐに購入して、生徒さんにこの勉強方法を取らせて下さい。